里親と“息子”の幸せな日々に、
突然訪れた“家族”のタイムリミット
彼らが選んだ未来とは――
実話に基づく感動作

監督の少年時代の体験を基に映画化
フランスの里親制度から
“家族のかたち”を描く感動作
長編デビュー作『ディアーヌならできる』が、第9回マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルで映画監督審査員賞を受賞したファビアン・ゴルジュアール監督。2作目となる本作は監督が子どもの頃、両親が生後18ヶ月の子どもを里子として迎えて6歳まで一緒に暮らした経験を、記憶を掘り起こしながら映画化したもの。もうひとつ物語のモデルとなったのは、監督が福祉関係者や里親とのインタビューで知った父と息子のエピソードだ。子どもが誕生後すぐに母親が亡くなり、打ちのめされた父親は子どもと引き離されてしまったという。里親制度をサポートする組織や里親の役割もリアルに紹介され、子どもの幸せを願う周囲の温かさが伝わってくる。監督が複雑な愛情関係を脚本に落とし込む中で参考にしたのは、『キッド』、『クレイマー、クレイマー』、『E.T.』の傑作群。深い愛で結ばれた絆と別れのエッセンスが、本作の隅々まで行き渡っている。
愛情豊かで賑やかな里親家庭と、実父の間で揺れる少年シモンを演じるのは、演技初挑戦のガブリエル・パヴィ。公園で母親と遊んでいたところ、監督とキャスティング・ディレクターによって見出されたという。映画初出演にして一躍スターダムにのしあがった『存在のない子供たち』のゼイン・アル=ラフィーアや『ミナリ』のアラン・キムに継ぐ、新たな天才子役が誕生した。里親のアンナには、『海の上のピアニスト』のメラニー・ティエリー、夫のドリスには『キャメラを止めるな!』のリエ・サレムら実力派が出演。
今は一緒にいなくても、血がつながってなくても、家族だった時間は消えない。さまざまなかたちの家族にエールを送る奇跡の物語。
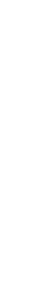
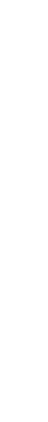
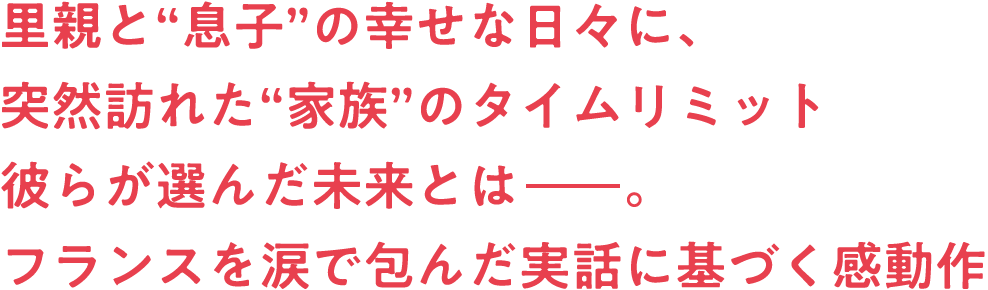

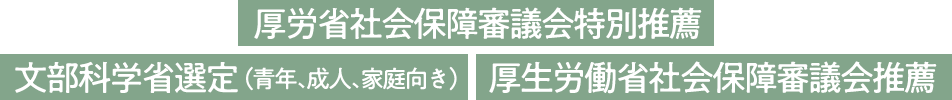




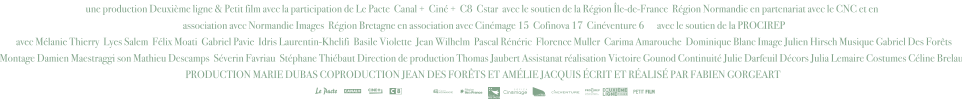

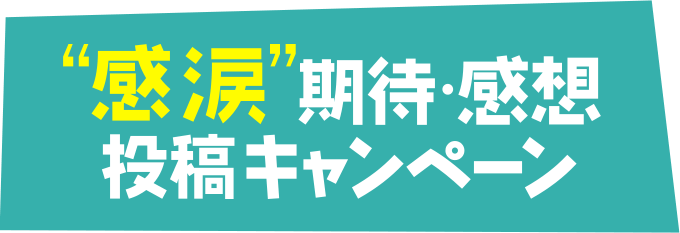

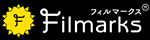























全てはその子の未来のために。
里親制度は完璧ではないかもしれない。
でもシモンが里親から受けた愛情は生きている。
シモンにはこの愛が必要だった。
日本ではまだ里親の数は少ないが、どう支援制度を整えるべきか、考えるきっかけが生まれる作品だ。
犬山紙子(イラストエッセイスト)
里親のアンナの傍に寄り添っていたかった。大丈夫じゃないのに笑顔を見せるのも、愛しすぎて身勝手になるのも、ひとつひとつが苦しいほど刺さってくる。
そしてラストシーン、“本当の家族”のあたたかい眼差しに触れました。
豊田エリー(俳優・モデル)
私たち「養育里親」の立場が曇りなくストレートに描かれ、ラストは胸が詰まる。
でも私たちは、それでもなお、子どもたちを愛し続けます。
藤井康弘(全国家庭養護推進ネットワーク代表幹事、養育里親)
ふたつの家族で育ったシモンは、どんな大人になるのかな。
里親家庭の母親目線で観ると、突然のお別れはつらくてつらくて涙が止まらなかった。
だけどみんな、シモンのことを一番に考えてる。
制度の中には必ず人がいて、そこにはたくさんの感情があるということを、いつだって忘れずに生きていきたい。
ふくだももこ(映画監督/小説家)