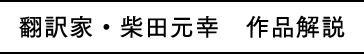柴田元幸(アメリカ文学研究者・翻訳者)

1920年代はアメリカが激変した時代だった。1918年に終わった第一次世界大戦でヨーロッパは戦勝国も敗戦国も疲弊し、経済的にはアメリカの独り勝ちとなった。20年代この国は未曾有の好景気を迎え、大半の人が生活に最低限必要な以上の品物を所有できるようになって、人が生産者である前に消費者として生きる、という現代社会の原型がこの時期に成立した。消費が悪徳ではなく美徳となった「ジャズ・エイジ」にあっては、風俗も大きく変化し、短い髪、短いスカート、煙草をくわえた新しいタイプの女性「フラッパー」が都会に出現した(むろん、年上の真面目な人々や田舎の人々の顰蹙(ひんしゅく)を買ったわけだが)。
そうした大衆社会の出現に合わせて、文化も単に一部の金持ちが享受するものではなくなった。野球、映画、ジャズといった大衆文化が広まり、ベーブ・ルース(野球)、ルドルフ・ヴァレンチノ(映画)、チャールズ・リンドバーグ(大西洋単独横断飛行)といった大衆的ヒーローが出現したのもこの時代が最初である。
全体としては華やかな時代だったが、「すべての戦争を終わらせる戦争」と言われた世界大戦が終わっても安定した平和は訪れず、ある種の失望感・喪失感もそこには漂っていた。当時の若い作家たちを指して「失われた世代(ザ・ロスト・ジェネレーション)」と呼んだのもこのためである。20年代アメリカを乱暴にまとめれば、「華やかさの陰に暗さを抱えていた時代」と言ってもいいかもしれない。それが、1929年10月に株価が大暴落し、繁栄は一気に終わりを告げて、ふたたび乱暴にまとめれば「誰もが腹を空かしていた時代」である1930年代に入っていく。

劇的に変化した時代にあって、文学も大きな変容を遂げた。題材も新しければ文体も新鮮な作品がこの10年でいくつも現われることになる。1920年、F・スコット・フィッツジェラルドが第一作『楽園のこちら側』を発表し、ジャズ・エイジの若者たちの風俗を、彼らが感じている空虚さも含めて描き、新人作家の作品としては異例の売れ行きを示した。1926年、アーネスト・ヘミングウェイが、「何をしたらいいかわからない若者が世界をさまよう」という、その後無数に書かれることになる物語の最初の成果『日はまた昇る』を刊行。そして1929年、トマス・ウルフが壮大な自伝的物語『天使よ故郷を見よ』を出版し、自分を通して世界のあらゆる側面を取り込もうとするアメリカ的野心を体現してみせた。
作家名・作品名はまだまだ挙げられるが、それ以上に重要なのは、これらの作家を世に出した編集者の存在である。マクスウェル・パーキンズは、出版歴ゼロ(もしくはほぼゼロ)だったフィッツジェラルド、ウルフ、ヘミングウェイらの才能を見抜いて、彼らを励まし、原稿をどう直したらいいか的確なアドバイスを与えたばかりか、私生活でも彼らを支えたのである(浪費家だったフィッツジェラルドが野垂れ死せずに済んだのも、パーキンズの小まめな援助のおかげである)。
パーキンズが編集者として働きはじめたころのチャールズ・スクリブナーズ・アンド・サンズは、ヘンリー・ジェームズ、イーディス・ウォートンといった大御所を抱えた老舗出版社であり、編集者の役割はコンマやピリオドの位置を調整し誤字脱字を拾うといった域を超えないことも多かった。文学の新しい流れを切り拓こうという気概はなかった。パーキンズ自身、ニューイングランドのそこそこにいい家の育ちで、べつに小さいころから反逆児であったわけではなかったが、社の最若手編集者として新しい作家を発掘することには熱心だった。ひとたび作品が完成してからは、年長の人たちを辛抱強く説得し、何とか出版まで漕ぎつけた。いまでこそヘミングウェイやウルフは文学史に名を残す大家だが、当時は――特に上の世代から見れば――小説の書き方もろくに知らない不届きな若造でしかなかったのである。1925年のこと、スクリブナーズのある年配社員は、自社新刊のあるページを震える指で指し、「うちの社がこんな言葉の入ってる本を出すなんて!」と憤った。その本とはスコット・フィッツジェラルド著『グレート・ギャツビー』であり、「こんな言葉」とは「サノバビッチ(クソッタレ)」だった。

作家の執筆を助け私生活でも助けたパーキンズだが、彼に助けられた度合いが誰よりも大きかったのがトマス・ウルフである。身長2メートル、体重110キロ超の超大食漢だったウルフは、書き手としてもすさまじいエネルギーの持ち主で、無限に言葉を紡ぎ出すことができた。だが彼は、それを出版可能な長さと形にまとめる能力をまったく欠いていた。その能力を提供したのがパーキンズである。30万語(日本語400字換算で2000枚弱)近くあった第一長篇『失われしもの』の草稿は、パーキンズの丹念な指導により約6万語削られて『天使よ故郷を見よ』として出版された。パーキンズの手が入る前の『失われしもの』は2000年に発表されたので、現在では両バージョンを比較することが可能である(僕も読んだが、何ぶん間に何年か入っていたので、とにかくどちらも圧倒的な読書体験だったと言うことしかできない。少なくとも、『失われしもの』の刊行でまったく違うウルフ像が現われたということはないと思う)。
第二作『時と川の』を、第一作以上に徹底的なパーキンズとの共同作業を経て出版したのち、ウルフはパーキンズから離れて、別の編集者・出版社と組むことになる。その経緯はきわめて複雑だが、基本的には、ウルフがパーキンズという父から離れ子として独立しようとしたと考えればいいのではないかと思う。父を超えることはアメリカ文学の大きなテーマでもある。
ひとたび父を超えた子は、時にはやがて父に回帰する。ウルフは死の床にあって、パーキンズに――今回の映画でも美しく再現されているとおり――長い感謝の手紙を書いた。そして遺言でも、パーキンズを著作権管理者に指名した。ウルフもまた、父に回帰したのだ。